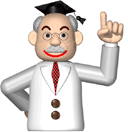
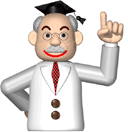
 定期借家は、賃貸人(貸主)・賃借人(借主)それぞれにとってどのようなメリットがありますか。教えて下さい。
定期借家は、賃貸人(貸主)・賃借人(借主)それぞれにとってどのようなメリットがありますか。教えて下さい。 定期借家(定期建物賃貸借)契約は、貸主と借主が合意に基づいて、自由に契約期間、家賃等を決めて、契約期間の満了によって契約が終了するものです(再契約は当然可能です)。
定期借家(定期建物賃貸借)契約は、貸主と借主が合意に基づいて、自由に契約期間、家賃等を決めて、契約期間の満了によって契約が終了するものです(再契約は当然可能です)。
定期借家は、「貸主と借主が対等な立場で契約期間や家賃等を決め、合意の上で契約が行われる自由な賃貸借契約制度」です。
現在行われている正当事由による解約制限のある賃貸借契約とは異なり、契約期間が満了すると、更新されることなく、確定的に賃貸借契約が終了する新しい賃貸借契約制度です。
定期借家契約は、家賃、期間等が当事者の合意で自由に契約できますので、借家の需要者(借主)と供給者(貸主)の自由な選択によって調整される市場原理に則した新しいタイプの賃貸借契約といえます。
英米では、定期借家契約が一般的ですから、我が国の借家市場も国際標準(グローバル・スタンダード)に対応した時代が到来することとなります。
定期借家は、契約によって、期間や収益に関する予測可能性も高まり、賃貸人の経営意欲も高まりますので、広くて、安い賃貸住宅の供給も大いに期待できます。
従来型の賃貸借契約は、基本的に戦前の昭和16年制定の借家法に基づいた仕組みのまま今日に至っているものです。これには、特に、戦中戦後の住宅不足の時代において借家人保護の役割を果たす意味がありましたが、近年は正当事由による弊害や高額な立ち退き料の問題等が目立ち、借家市場の歪みが著しいものと認識されています。
定期借家制度の導入によって、このような現行の賃貸借契約制度による借家市場の歪みを解消し、広くて、安い家賃の賃貸住宅が多く供給されることが期待でき、借手にとっても多様な賃貸住宅の中から、自らのライフステージ、ライフスタイルに見合ったものを選択できることとなります。
また、貸主においても、契約期限が来たら契約は終了し、明渡しが可能となりますが、反面、個々の賃貸マンション・アパートが借手の厳しい選択の対象となるため、賃貸住宅経営は厳しい競争の時代に入るでしょう。今までのような地理的条件さえ良ければ、いくらでも借手がつくような時代ではなくなります。
このことは、規制と保護から選択と責任をより重視するものであり、貸主と借主間で一定の良好な緊張関係が形成されることとなりますので、借家市場の活性化につながるものと期待されています。
平成11年7月30日、自民党・自由党・公明党の3党の共同提案により、良質な賃貸住宅の供給促進と定期借家制度の導入を柱とした「良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法案」が国会に提出されました。さらに、民主党の修正案を取り入れて、同年11月19日に、4党で衆議院建設委員会に修正提案を行い11月24日附帯決議を付し可決、11月25日衆議院で可決、12月7日参議院国土・環境委員会で可決。同年12月9日参議院で可決・成立しました。
この新法は、現在契約され、お住まいになられている方々へのセーフティネット(弱者保護)についても考慮がなされた法律となっています。
借地借家法の改正内容の主な点を列挙しますと、以下のとおりです。